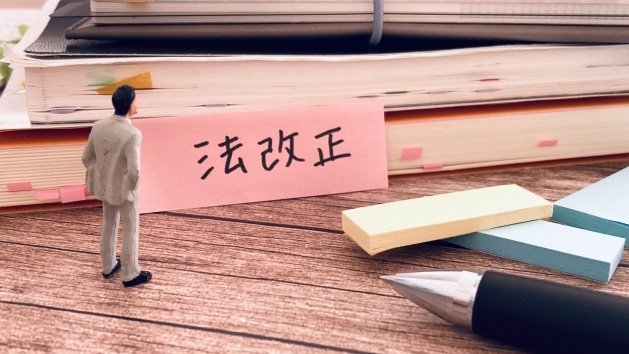| 通達名 | 労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和6年4月26日基発0426第2号) |
| 通達日 | 令和6年4月26日 |
| 詳細 | 労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について |
改正の背景
令和6年1月31日付で、労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
本通達では、「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第2条の規定の施行について」、「特別加入者に係る業務上外の認定及び支給制限の取扱いについて」等に定めるもの以外に留意すべき事項を通達します。
改正の概要
1,基本事項
■改正の趣旨及び概要
労働者災害補償保険法における労災保険の特別加入の制度については、国民の意見や関係団体からのヒアリングの上、順次個別に事業や作業を特定した上で、特別加入制度の対象を追加してきたところである。
一方、フリーランスの事業や作業内容は多様で、新しい形の事業や作業を行う者が幅広く労災保険に加入できるよう、制度の見直しが課題となっている。
今回の特別加入の対象の拡大に当たっては、フリーランスが幅広く加入できるよう、「フリーランス法に規定する特定受託事業者が、業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から同種の事業について物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供の委託を受けて行う事業を含む)」を新たに特別加入の対象事業とすることとした。
なお、フリーランス法の施行の日前に発生した業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害による負傷、疾病、障害又は死亡に起因する保険給付については、なお従前の例によるものとする。
■実施期間
今回の特別加入の新設に関する改正省令は、フリーランス法の施行の日から施行される。
2,特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入の新設(労災則第46条の17第12号関係)
■加入対象事業
特定受託事業者が業務委託事業者から特定受託事業又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、労災則第46条の17第1号から第11号までに掲げる事業及び労災則第46条の18各号に掲げる作業を除いたもの。(以下、「特定フリーランス事業」)
■加入対象者
ア 加入対象者は、下記いずれかに該当する者であること。
⑴労働者以外の者であって、特定フリーランス事業を労働者が使用しないで行うことを常態とする者
⑵労働者以外の者、上記⑴が行う事業に常態として従事する者
イ ここで、「特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定委託受託事業と同種の事業であって、労災則第46条の17第1号から第11号までに掲げる事業及び労災則第46条の18各号に掲げる作業を除いたもの」について、消費者のみから委託を受けて事業を行う者は対象とならない。
ただし、消費者のみから委託を受けて事業を行う者であっても、事業者から業務委託を受けて事業を行う意向を有する場合には、対象となること。
また、事業者から業務委託を受けて行う事業とは異なる事業について、消費者から委託を受けて行う者は対象とならない。
■保険料率及び特定業種区分
第2種特別加入保険料率は1000分の3、事業の種類の番号は特12とされた。(徴収則第23条及び別表第5)
■特別加入団体の手続
ア 特別加入の承認に係る手続き
特別加入の承認に係る手続は、以下に定めるもののほか、一人親方その他の自営業者とその事業を行う者に係る特別加入の承認に係る手続(※)によること。
※基本通達記の第2の4(第2の4の⑶については、第2の3⑷のイに係る部分に関する者を除く。)、7及び8参照
イ 特別加入の承認に係る手続の留意点について
特定フリーランス事業の特別加入の承認は、基本通達記の第2の6⑵(同ホに掲げるものを除く)の基準に加え、下記(ア)~(エ)のすべての基準に適合する場合に行うこと。
(ア)加入申請者たる団体(当該団体の母体となる団体を含む)が、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動の実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有していること。
特定フリーランス事業の対象業務は広範囲にわたることから、特定フリーランス事業の団体にあっては、極めて広範な業務を行う加入希望者に対する相談や、加入後の支援に当たることとなり、当該者の業務内容や被災実態について広く精通している必要があり、これを裏打ちする活動実績を求めるものである。
(ア)の要件について、「母体となる団体」とは、加入申請者たる団体の定款等において、出資者として記載のある団体又は役員、評議員等の出身団体として記載のある団体など、加入申請者たる団体との関係性が確認できる団体を指すこと。
「フリーランス」とは、フリーランス法の施行の日より前に、特定フリーランス事業を行う者を含むこと。
「特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動」とは、特定フリーランス事業を行う者等を対象として、業務災害防止のための啓発、取引の安全確保に係る支援等の活動が継続的に行われているものであること。
「活動期間」とは、加入申請者たる団体の規約等において活動の開始時期を明示しているもの等、実態として「特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動」を開始したことがわかる時点を始点とするものであること。
加えて、「100名以上の会員等」とは、特別加入団体としての申請の時点で当該団体に100名以上の会員等がいることであること。
(イ)全国を単位として団体を運営すること。その際には、都道府県ごとに加入を希望する者が訪問可能な事務所を設けること。
特定フリーランス事業を行う者は多数に及ぶことが想定され、またその業務の範囲も幅広い中、フリーランス法案の三喜院内閣委員会附帯決議においては「希望するすべて」のフリーランスが特別加入できるよう対象範囲を拡大することとされる。また、いわゆる「フリーランス」の年齢層については50歳以上の割合が50%を占めるとの調査結果もあり、対面での情報提供や申請を望む者も一定程度存在することが想定されることも踏まえれば、より多くの特定フリーランス事業を行う者が安心して加入できるようにするために、オンライン以外の方法による支援も可能とすることが望ましく、訪問可能な事務所を設けることを要件とするものである。また、事務所の設置単位については、全国各地の特定フリーランス事業を行う者に対して支援を行う必要があること等から、都道府県単位で事務所を設けることを求めるものである。
(イ)の要件について、「訪問可能な事務所」とは、相談員の常駐は要しないものであるが、賃貸借により事務所を使用する場合には賃貸借契約、シェアオフィス等を使用する場合にはメンバーシップ契約等により十分な利用時間が確保されていること。
(ウ)加入を希望する者等に対し、加入、脱退、災害発生時の労災給付請求等の各種支援を行うこと。
特定フリーランス事業を行う者は、その業務の範囲が広範にわたることから、他の特別加入の事業又は作業と兼業している者も存在すると予想される。このため、特別加入団体は、加入希望者の相談に応じた上で、当該者の行う業務が特定フリーランス事業に該当するか、あるいはほかの特別加入の事業又は作業に該当するかといった情報提供を行う必要がある。また、特定フリーランス事業を行う者の業種や年齢層は幅広いものになると考えられ、各種申請時の相談内容も多岐に及ぶとみられること、また、いわゆる「フリーランス」は推計273万人であるとの調査結果があることや加入・脱退といった構成員の変動も大きいと想定されることから、特定の業種のみを対象とする特別加入団体に比べて特定フリーランス事業を行う者に対して一番手厚い支援を求めるものである。
(ウ)の要件について、「各種支援」は、具体的に以下のような支援が想定されること。
- 特定フリーランス事業以外の特別加入の事業や作業を行う者が、特定フリーランス事業を行う者として加入を申請しようとした場合には、特定フリーランス事業以外の特別加入の事業や作業を行う者として特別加入するように情報提供すること。
- 特定フリーランス事業以外の特別加入の事業や作業を行う者が、特定フリーランス事業を行う者にも該当する場合は、いずれの事業又は作業においても労災保険の適用を受けるためには、特定フリーランス事業以外の特別加入の事業又は作業と特定フリーランス事業の両方に特別加入する必要があるため、特定フリーランス事業を行う者の特別加入申請を受け付ける際には、当該事項について周知すること。
- 特定フリーランス事業を行う者に対し、形式上は「請負」や「委任」の契約形態であったとしても、実態として労働者と同様の働き方をする場合には、労働者として保護される旨を周知すること。
- 労災請求に当たって、特定フリーランス事業を行う者が提出することとなる請求者等の作成支援を行うこと。
(エ)加入者に対して、適切に災害防止のための教育を行うこと。
特定フリーランス事業を行う者の業種や年齢層は幅広く、特別加入団体は加入者に対して適切に災害防止教育を行う必要がある。
(エ)の要件について、「災害防止のための教育」は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して当該団体が主催する災害防止等に関する研修会等(双方向の質疑応答を含むオンライン形式を含む)への参加の機会を提供するものであること。
なお、「当該団体が主催する災害防止等に関する研修会等(双方向の質疑応答を含むオンライン形式を含む)」の実施に当たりテキストを用いる場合には、追って、厚生労働省のHP上で掲載することを予定しており、必要に応じて活用を促すこと。
また、(エ)の確認については、別途通知するところにより特別加入団体に報告させること。
ウ 特別加入団体及び特別加入申請者の申請受理の特例
特別加入の申請に対する所轄都道府県労働局長の承認は、基本通達記の第2の4(3)の通りとし、特別加入の申請の日の翌日から起算して30日の範囲内において申請者が加入を希望する日とする。
ただし、基本通達の第2の4(3)中、基本通達記の第2の3(4)イに係る部分にかかわらず、特別加入の申請に対する所轄都道府県労働局長の承認については、令和6年9月2日から同年10月1日までに特別加入団体に係る書類の提出があった場合は、当該書類における「加入を希望する日」がフリーランス法の施行の日とされているものに限り、これを受理することとすること。
エ 特定フリーランス事業の特別加入団体の承認に係る手続きに関して必要な事項は別途通知する。
■災害の認定基準
ア 業務災害の認定
(ア)業務遂行性は次の行為を行う場合に認めるものとする。
a 契約に基づき報酬が支払われる作業のうち特定フリーランス事業に係る作業及びこれに直接附帯する行為(※)
※「直接附帯する行為」とは、生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいう。
注1:「特定フリーランス事業に係る作業」とは、特定受託事業者が行う作業のうち、業務委託を受け契約を締結してから最終的な物品、情報成果物又は役務の提供に至るまでに必要となる作業をいう。ただし、自宅等で行う場合については、特に私的行為、恣意的行為ではないことを十分に確認できた場合に業務遂行性を認めるものとする。
注2:「直接附帯する行為」としては、例えば、契約を受注するための営業行為、契約締結に付随する行為及びその事務処理等が該当する。
b 契約による作業に必要な移動行為を行う場合(通勤災害の場合を除く)
(例)契約を締結するための事前打ち合わせに係る移動、業務委託事業者又は業務委託事業者以外の者からの指示による別の作業場所への移動等
c 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上の場合
(イ)業務起因性は、労働者の場合に準ずること。
イ 通勤災害の認定
特定フリーランス事業を行う者の住居と就業の場所との間の往復を想定し、通勤災害についても労災保険の対象都市、通勤災害の認定については、労働者の場合に準ずること。
■中小事業主等の特別加入との関係
ア 基本通達記の3(2)と同旨であるが、労働者を使用して事業を行う場合は労災則第46条の17第12号に基づく特定フリーランス事業を行う者としては該当しないことから、労災保険法第3条第1号に基づく中小事業主として特別加入すること。
イ 労災保険法第33条第2号に基づく中小事業主等が行う事業及び特定フリーランス事業を行う者については、それぞれの加入要件を満たせば、本人の選択によりいずれにも特別加入できることとなるが、重複加入は認められない。したがって、特定フリーランス事業に関し中小事業主等として特別加入している者が、特定フリーランス事業を行う者として特別加入する場合(あるいは逆の場合)は、委託解除届を確認する等、重複期間が生じないように留意すること。
なお、誤って重複加入した場合は、先に加入した特別加入が優先し、後から手続した特別加入に係る保険関係は無効となることに十分留意し、特定フリーランス事業を行う者に係る特別加入の申請を受け付ける際には、特別加入予定者が中小事業主等として特別加入していないか確認の上、中小事業主等として特別加入している者がある場合は、必ずその脱退の申請又は届出を同時に提出するよう指導すること。
■一人親方等及び特定作業従事者との関係
ア 基本通達記の4(2)と同旨であるが、労災則第46条の17第1号から第11号まで及び労災則第46条の18各号において規定する事業又は作業については、特定フリーランス事業としては業務遂行性が認められない。
従って、特定フリーランス事業への加入を希望する者等が行う業務が、労災則第46条の17第1号から第11号までにおいて規定する事業及び労災則第46条の18各号において規定する作業のいずれかに該当する場合には、当該事業又は作業に係る特別加入団体を通じて加入する必要があること。
イ 労災則第46条の17第1号から第11号まで及び労災則第46条の18各号において規定される事業又は作業と特定フリーランス事業については、その業務遂行性が認められる範囲が異なるため、そのいずれも行う場合において、それぞれの事業又は作業で労災保険の適用を受けるためには、それぞれで特別加入をしていることが必要となる。
よって、新たに特別加入申請書を提出する特別加入団体に対しては、当該事項について積極的に周知すること。
3,新設した事業に係る一般事項及び当面の事務処理について
■一般事項
ア 保険給付の請求
保険給付に関する事務は、当該特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行う。(労災則第1条第3項)
イ 保険給付の支給制限
保険給付の支給制限については、昭和40年12月6日付飢渇第1591号通達の記の第2による。
ウ 特別加入団体及び特別加入者の申請受理の特例
本通達記の2「特別加入団体の手続」のウに記載の通り。
エ 特定フリーランス事業に係る特別加入の承認等については、対象業務が広範にわたること等から、加入申請者たる団体は、全国各地において特定フリーランス事業を行う者の保護のための支援を丁寧に行うとともに、当該者に対し、災害防止のための措置を適切に講じる必要がある。
特定フリーランス事業の特別加入の承認を受けた団体に対しては、厚生労働省労働基準局から、労災部会において、災害防止措置等に関して説明を依頼することが予定されている。
■当面の事務処理
ア 労働者性に係る周知
特別加入申請書の提出があった場合は、加入申請者たる団体に対し、形式上は「請負」や「委任」の契約形態であったとしても、実態として労働者と同様の働き方をする場合には、労働者として保護される旨を積極的に周知する。
イ 特別加入団体における被災状況等の把握に係る周知
団体の構成員たる加入者が被災した場合は、特別加入団体において、加入者から聞き取りを行う等により災害発生状況の把握に努め、実態を踏まえた災害防止措置を行うよう積極的に周知する。
ウ 特別加入システム等における機械処理
特別加入システム及び労災サブシステムにおける機械処理については別途通知。
4,関係通達の改正
■基本通達の改正
■昭和40年12月6日付基発第1591号通達の改正
改正による影響
フリーランス法は2024年秋頃施行予定となります。
事業主や人事担当者は、留意事項をよくご確認の上、適切な事務処理を行えるよう、準備を進めてください。