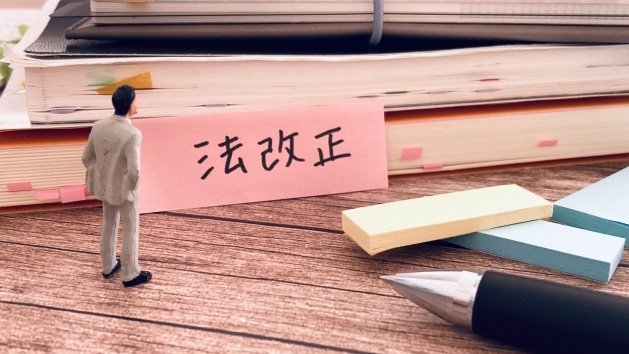| 通達名 | 令和7年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項 |
| 通達日 | 令和7年3月28日 |
| 詳細 | 通達 令和7年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項 |
改正の背景
昨年の建設業における労働災害発生状況は、前年同期の212人と比べ6.6%程度増加となるものの、前年の次に少ない件数となる見込みです。
しかし、全産業に占める建設業の労災発生割合は31.2%と、依然として業種別で最も高い割合となっています。
本通達では、建設業の安全衛生対策の推進を図るために、各行政機関や事業所に留意事項をお知らせするものです。
改正の概要
下記では、事業者向けの留意事項を抜粋して掲載しています。
1.労働者の安全確保のための対策
(1)墜落・転落災害防止対策
一側足場の使用範囲の明確化、足場の点検を行う際の点検者の指名の義務化などを内容とする改正労働安全衛生規則(令和5年厚生労働省令第22号。以下「改正安衛則(足場関係)」)の全面施行、改正「手すり先行工法に関するガイドライン」の策定等を踏まえ次の対策を推進する。
ア 足場等からの墜落・転落防止対策
改正安衛則(足場関係)に基づき、本足場の使用や、足場の点検者の指名等の措置を講じるとともに、改正「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく措置を適切に講ずること。また、墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組むこと。
さらに、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」(平成 24年2月9日付け基安発 0209 第2号、令和5年3月 14 日最終改正)に基づき、わく組足場における「上さん」の設置、「足場等の種類別点検チェックリスト」の活用、足場の組立て等の後の点検について、十分な知識・経験を有する者による点検の実施に取り組むこと。
木造家屋等低層住宅建築工事においては、「木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル」に基づく措置を適切に実施すること。
イ はしご・脚立からの墜落・転落防止対策
木造家屋等低層住宅建築工事においては、上記マニュアルに基づく措置を適切に実施するとともに、リーフレット「はしごを使う前に/脚立を使う前に」、「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう!」等を活用し、はしごや脚立の使用をできるだけ避け、移動式足場や高所作業車を使用すること、はしごや脚立の安全な使用方法を徹底すること等、墜落・転落災害防止に取り組むこと。
ウ 墜落制止用器具の適切な使用
「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に基づき、墜落制止用器具の適切な使用を徹底するとともに、墜落制止用器具の使用状況を確認し必要な措置を講じること。また、「墜落制止用器具の規格」に適合した墜落制止用器具の使用を徹底すること。
(2)令和6年能登半島地震等の自然災害の復旧・復興工事における労働災害防止対策
自然災害に係る復旧・復興工事では、多数の建設業者により短期間で集中的な工事が行われること、建物の崩壊や地盤の緩み等、作業場所の状態が平常時と異なること等から、災害発生のリスクが高い状況にあることを十分に認識し、土砂崩壊防止措置や墜落転落災害防止措置等、労働安全衛生法令や関係のガイドライン等に基づく措置を徹底すること。
また、復旧・復興工事では、被災県以外の建設業者が工事を行い建設業者間の情報共有が十分でない場合があること、災害ボランティア等の建設業者以外の者が作業範囲に立ち入る可能性もあること等から、隣接する工事現場での建設業者間の情報の共有(災害防止連絡連絡協議会等)に努めるとともに、建設機械との接触防止措置の徹底等、必要な措置を講じること。
(3)高年齢労働者の労働災害防止対策
エイジフレンドリーガイドラインに基づき、高年齢労働者の就労状況等を踏まえた安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等の取組を進めること。
(4)外国人労働者の労働災害防止対策
外国人労働者に対する安全衛生教育を行う場合には、これらの教材を活用しつつ、外国人労働者がその内容を確実に理解できる方法で実施すること。
また、外国人労働者が労働災害に被災した場合に労働者死傷病報告を提出する際、被災労働者の国籍・地域及び在留資格を、在留カード等により確認し、記入すること。
(5)一人親方等の安全衛生対策
建設業に従事する一人親方等については、上記研修会等に積極的に参加すること。
改正内容について、事業者の理解を進めるとともに、同改正で保護対象となる一人親方等に適切に周知すること。
(6)転倒災害防止対策
リーフレット(https://www.mhlw.go.jp/content/001101746.pdf )等を活用し、転倒災害防止のための労働者の身体機能の維持向上や職場環境の改善に取り組むこと。
(7)交通労働災害防止対策
上記ガイドラインに基づく措置を適切に講ずること。
とりわけ、建設資材等の運搬を発注する際は、過積載運行にならないよう実際に荷を運搬する事業者に協力すること。
(8)車両系建設機械等による労働災害防止対策
労働者に車両系建設機械を使用させる場合は、労働安全衛生規則に基づき、運行経路等を示した作業計画を定め、関係労働者に周知するとともに、車両系建設機械の転落、接触等により労働者に危険が生じるおそれのある場合は誘導者を配置するなど、必要な安全対策を講ずること。
(※)令和7年1月速報時点。
(9)安全な建設機械の普及
「車両系建設機械構造規格」に適合した建設機械を使用するとともに、上記補助金の活用を積極的に検討すること。
(10)荷役作業における労働災害防止対策
改正安衛則(貨物自動者関係)に基づき、昇降設備の設置及び保護帽の着用の徹底を図るほか、必要な労働者に対しテールゲートリフターの操作に係る特別教育を実施すること。また、リーフレット「荷役作業の安全確保が急務です!」(令和3年1月18日付け基安安発0118第2号)に示す取組を実施し、荷役災害防止対策を適切に講ずること。
(11)交通誘導等の警備業務における労働災害防止対策
建設工事の現場等で交通誘導等に従事する労働者に対する安全衛生教育を実施する場合には、同マニュアルを活用すること。
(12)山岳トンネル工事における労働災害防止対策
山岳トンネル工事の発注者においては、同ガイドラインに基づき、設計段階における適切な支保パターンの選定のほか、施工段階における地山の状況に応じた設計の変更等の必要な対応を行うこと。また、施工者においては、同ガイドラインに基づき、鏡吹付の実施、切羽への立入禁止措置の徹底、切羽監視責任者による監視等、肌落ち災害防止対策を適切に講じること。
また、現場内は狭あいな箇所で重機等が稼働することから、作業員と重機等との接触防止対策についても確実に講じること。
(13)伐木等作業における労働災害防止対策
チェーンソーによる伐木等作業を行う場合にあっては、対象労働者へ
の特別教育を実施するとともに、立入禁止措置や保護具の着用等の安全
対策を適切に実施すること。
(14)専門工事業者等の安全衛生活動支援事業
専門工事業者等は、上記事業を活用する等により、自主的に安全衛生活動を行うこと。
(15)建設工事関係者連絡会議の運営等
(16)建設職人基本法・基本計画に基づく取組等
2.労働者の健康確保のための対策、化学物質等による労働災害防止対策
(1)メンタルヘルス対策
ストレスチェック制度の実施を徹底するとともに、労働災害を防止する上でもメンタルヘルス対策が有効との調査結果(建災防実施)もあることから、建災防とも連携して、建設工事の現場等におけるメンタルヘルス対策を適切に講ずること。
なお、事業主団体等や労災保険の特別加入団体については、当該団体が、傘下の中小企業や労災保険の特別加入者(一人親方等)等に対して、ストレスチェックやストレスチェック後の職場環境改善支援等の産業保健サービスを提供する費用の一部を助成する「団体経由産業保健活動推進助成金」が活用できるものであること。また、独立行政法人労働者健康安全機構が運営する、産業保健総合支援センター及
び地域産業保健センターによる産業保健支援サービスを無料で活用できること。
(2)熱中症対策
「職場における熱中症予防基本対策要綱」を踏まえ、暑さ指数の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること。また、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより重篤化を防止するため「報告体制」、「手順作成」、「関係労働者への周知」を実施すること。あわせて、作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うほか、衛生管理者等を中心に事業場としての管理体制を整え、発症時・緊急時の措置を確認し、周知する。その他、熱中症予防に効果的な機器・用品の活用も検討すること。
また、労働者は、熱中症を予防するために、日常の健康管理を意識し、暑熱順化を行ってから作業を行うこと。あわせて、作業中に定期的に水分・塩分を摂取するほか、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出ること。なお、前述の「団体経由産業保健活動推進助成金」が活用できるものであること。
(3)じん肺予防対策
粉じん濃度の測定、換気装置等による換気の実施等、また、発注者は必要な経費の積算等、第 10 次粉じん障害防止総合対策に基づき適切にずい道等建設工事における粉じん対策を講ずること。
当該防止総合対策に基づく措置を適切に講ずること。また、解体作業等において、法令上必要であるにもかかわらず現場監督など事業者側の判断により防じんマスクを外させることなく、労働者に防じんマスクを確実に使用させること。
(4)騒音障害防止対策
事業者は、ガイドラインに基づき屋内作業場に限らず、騒音障害防止対策の管理者の選任、騒音レベルの把握とその結果に応じた騒音ばく露防止対策、健康診断、労働衛生教育等に取り組むこと。また、元方事業者においては、関係請負人が本ガイドラインで定める事項を適切に実施できるよう、指導・援助を行うこと。なお、前述の「団体経由産業保健活動推進助成金」が活用できるものであること。
(5)化学物質による健康障害防止対策
建設業においても、塗装や作業に使用する製剤など多くの化学物質を用いていることから、店社ごとに化学物質管理者を選任し、使用前にラベル・SDS を確認させ、その情報に基づき、当該化学物質を用いる作業に応じたリスクアセスメント及び当該結果に基づく措置等を講ずること。その際、建災防が作成する化学物質管理に関する資料や管理マニュアル等を必要に応じ活用すること。
また、引き続き特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則等の遵守の徹底を図るため、作業主任者等に必要に応じ能力向上教育等を行うこと。さらに、保護具を着用する作業現場においては、店社ごとに保護具着用管理責任者の養成に留意すること。
塗膜剥離作業においては、塗膜には鉛、六価クロム、PCB 等の有害物が含まれうることにも留意し、有害物の含有状況や作業内容に応じて適切なばく露防止対策(剥離剤等作業で使用する保護具の着用も含む。)を講ずること。また、研磨材の吹き付け(ブラスト)や研磨材を用いた手持ち式動力工具(ディスクサンダー)による鋼構造物の研磨等においては、塗膜中の有害物の有無にかかわらず、粉じん障害防止規則に基づき、労働者に対して、呼吸用保護具(送気マスク等)を使用させる等の措置を講ずる
こと。
作業者に対して、ラベル等により作業に用いる化学物質の危険性・有害性や適切な保護具の使用について周知するようにすること。
(6)石綿健康障害予防対策
石綿障害予防規則に基づき、解体・改修工事前の石綿含有の有無の事前調査、石綿事前調査結果報告システムを用いた事前調査結果等の報告、写真等による作業の実施状況の記録の作成及び保存などの措置を徹底する。
また、令和5年10月1日以降着工の工事において建築物等の事前調査を実施するには有資格者に行わせることが義務付けられていることから、有資格者による事前調査を確実に行うこと。
さらに、令和8年1月1日以降着工の工事から工作物の事前調査を実施するには有資格者に行わせることが義務付けられることから工作物事前調査者講習の受講を計画的に行うこと。
3.その他の安全衛生に係る対策
(1)労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用
建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)を導入した企業の労働災害の減少幅は大きく、労働災害防止に効果があることから、建設工事現場の実態を踏まえたシステムである「ニューコスモス」、「中小事業者向けのコンパクトコスモス」の導入・活用に留意すること。
(2)建設業における安全衛生教育の推進
「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」(平成29年2月20日付け基発0220第3号)に基づき、建設業における職長等及び安全衛生責任者を対象に、概ね5年ごとに及び機械設備等に大幅な変更のあった場合に、建設工事従事者の専門性の確保のために、労働災害の防止に係る当該教育を受講させること。
また、「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育について」(平成15年3月25日付け基安発第0325001号)に基づき、建設工事に従事する労働者を対象に、建設現場で働く労働者が守らなければならない労働安全衛生法令の遵守事項等の基本的事項について教育を受講させること。
このほか、「安全衛生教育及び研修の推進について」(平成31年3月28日付け基発0328第28号)に基づく教育、その他の建設工事従事者の知識や能力の維持・向上のための再教育等の受講等に努めること。
改正による影響
企業のご担当者様は、通達の内容をよくご確認の上、必要に応じて対応および従業員への周知を行えるようにしましょう。